黒色火薬(その1)へ戻る
教科書的な黒色火薬の作り方
1.硫黄と木炭をボールミルに入れて、砕いて混ぜ合わせる
この作業を粉砕混和といい、2種類の原料を混ぜるので2味混和と呼びます。
ボールミルは、円筒形の容器の中に潰したい原料と硬いボール(セラミック製とか)を入れて、ひたすら容器を回転させて、ボールで原料を押しつぶしまくるツールです。
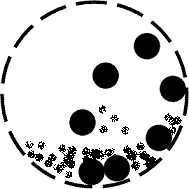
Lưu Ly(パブリックドメイン@Wikipedia)
2.2味混和した硫黄と木炭に、今度は硝石を混ぜて、更にボールミルで砕いて混ぜ合わせる
3種類の原料を混ぜるので3味混和と呼びます。
硝石も入ってくるといよいよ危険です。燃えやすくなってます。この時のボールミルは木製で、内側に革張りした特殊なヤツを使います。静電気や火花防止でしょうかね。混ぜる時には水も入れます。
3.圧磨機でゴリゴリすりつぶす
ボールミルから取り出したブツを石臼のような圧磨機(あつまき)でゴリゴリすりつぶします。
打撃や摩擦には鈍感な黒色火薬ならではですね。圧磨器は数トンもあるので水力で回転させます。

江戸幕府に命じられてオランダへ留学していた沢太郎左衛門という人が持ち帰った圧磨機(ベルギー製)です。
明治時代になってからは、旧加賀藩の下屋敷跡に作られた陸軍砲兵廠板橋火薬製造所で、石神井川の水を使って火薬を毎日ゴリゴリすりつぶしてました。
加賀藩といえば白川郷の火薬村。何か関係あるんでしょうかね。旧加賀藩士の火薬製造エキスパートを召し抱えたとか。下屋敷の敷地の中に秘密の火薬製造工場があったのを接収したとか。
なにせ板橋区ですからね。中山道の最初の宿場があったくらいなんで、それなりに江戸の街からは離れてたんだろうし。そのうち調べてみましょう。
陸軍砲兵廠板橋火薬製造所の跡地は加賀公園という公園になってます。圧磨機の記念碑は加賀公園から徒歩5分くらいのところにあります。
教科書的ではない黒色火薬の作り方
ガレージで火薬を作っているところを顔を晒してYoutubeに上げてるヤツがゴロゴロ。やっぱり英語圏すげーわ。
黒色火薬のいいところ
黒色火薬のいいところは、やっぱり作るのが簡単なところ。
明治時代になる前は手作りです。製造工程に化学反応を必要としないため、化学が未発達だった前近代でも作ることができたのです。
あと安全性と保存・運搬のしやすさ。衝撃や摩擦には鈍感なので移動・運搬も安全。
化学的に安定しているので自然分解もしにくく、保管中に他の物質に変わったりしない。濡れても乾かせば使える。
でも、火薬は火で乾かしちゃだめ
火薬が原因の事故は古今東西いっぱいありますが、イングランドの火薬陰謀事件は間抜けさが際立ってます(1605年、Gunpowder Plot)。
火薬陰謀事件は、カトリック派の貴族がプロテスタント(イングランド国教会)の国王を議会ごと(化学的にも物理的にも政治的にも)ふっとばそうとして、議事堂の地下室に火薬を仕掛けた事件とそれに連動した反乱です。
議事堂の方は実行直前に発覚して実行犯は現地で取り押さえられたのですが、同時に地方で反乱を起こそうとしていた連中が、雨で濡れた火薬を乾かすために焚き火にさらして(えー)大惨事。
議事堂のほうが失敗して焦ってたんですかね。首謀者たちは大やけどを負いながらも兵を挙げましたが、結局は捉えられて処刑。



絵の中の左の方、建物の手前で寝かされて捌かれている人。

黒色火薬の欠点
黒色火薬の欠点は、燃焼時の煙です。19世紀に登場した新型火薬が「無煙」火薬と呼ばれるくらい、それまでの火薬は煙がすごかった。
無煙火薬も煙が全く出ないわけではありません。でも、それまでの黒色火薬と比べると見た人がみんな感動するくらい少なかったから「無煙」と呼ばれたのでしょう。つまり、黒色火薬の煙それだけすごかった(今もすごい)。
火縄銃の実演を見ると分かる通り、結構な量の白い煙が発生します。
長篠の戦いみたいに大量の鉄砲が一斉に発射したら、煙幕ばりの煙に覆われてしまっていたことでしょう。
ナポレオン戦争やアメリカ独立戦争、日本の幕末など17世紀~19世紀の戦争映画を見ると、戦列歩兵が一斉に発砲するシーンで煙だらけになっていることがわかります。
この時代の軍服がオウムかよ?ってくらい派手なのは、煙の中で敵味方を識別するためだったという説もあるくらいです。

(パブリックドメイン@Wikiepdia)

(パブリックドメイン@Wikipedia)

(Flickr CC 表示-継承 3.0@Wikipedia)
もう一つの欠点は、硫黄を含んでいるため燃焼後に硫酸イオンが発生することと、燃焼後の生成物で簡単に詰まってしまうことです。
硫酸は、錆びにくいステンレスでも勝てないほど強力で、銃砲身や機構部分を腐食させてしまいます。
撃ったあとの銃砲はよく手入れしないと簡単に腐食してしまいますが、基地に戻ればできる手入れも、戦場ではそんな悠長なことやってられません。
燃焼後の生成物は、いわゆる煤(スス)です。
たかがススというなかれ。一発撃つだけで手や指で掻き出せるほどの量が発生するススを放っておくと、すぐに撃てなくなってしまいます。
やはりナポレオン戦争時代の戦列艦(帆船の軍艦)で、大砲を一発撃つたびにモップのような長い掃除道具を砲身に突っ込んでるシーンを、映画で見たことがある人もいると思います。
現代の黒色火薬
軍事利用という火薬界の花形(?)の座は次世代の火薬に譲った黒色火薬ですが、民生分野では今でも使い続けられているのは、黒色火薬ならではの有利な点もあるからです。
少量でも着火しやすく、熱を加えるだけ(火を付けるだけ)で着火できる簡便さ。燃焼ガスの発生速度が花火を打ち上げるのにちょうどよく、遅すぎず速すぎずと絶妙。
花火の他に、導火線の心薬としても使われています。
黒色火薬(その1)へ戻る